公開確認会(これまで)
公開確認会(これまで)
ももっこファーム山梨(2022年度)
■ 開催日
2022年8月19日(金)
■ 開催形式
オンライン
-
- 事前監査は8月18日(木)圃場にて実施。
■ 監査品目
ぶどう(種なし巨峰 or ピオーネ)
栽培基準_エコ・チャレンジ
産地概要
産地の特徴
甲府盆地の南東部に位置する全国屈指の果樹地帯。四季折々の豊かな自然に恵まれ、土壌は傾斜地で水はけがよく、盆地気候につき日中は暑く、夜は冷える為、果樹栽培に適している。

取り組み/商品特徴
- エコ・チャレンジ基準で栽培。更に、山梨県4パーミルイニシアティブを産地として取得し、環境に配慮した農産物として認証され、ブランド化している。
- 病害虫を防止する為に、疎植栽培を推進(収穫量は落ちる)。

設立趣旨
2019年3月、設立総会にて「ももっこファーム山梨」を立ち上げ、現在に至る。若手生産者の育成と活躍の場を増やし、近年の農業モデルを取り入れた未来へ繋げる農業生産を行う。
- 人にも環境にも配慮した循環型農業の未来を託す後継者たちに自由な発想と挑戦する場所を提供できたら、既存のメンバーも安心して任せられる。
- 既存の親世代が農業を営むうえでのアドバイス、経験を生かしたサポートを行い、若手とベテランが同じ意思を持ち、共に知識を高め、技術の研鑽をしながら生産活動を行える。
栽培品とメンバー構成(2022年8月現在)
- 桃、ぶどう、すもも
- 正会員8名(6戸)、総従業員数19名、家族農業で営んでいる。
- 総圃場面積は10㌶、圃場数は80~100程度。

産地理念
化学合成農薬の使用を抑え有機肥料を使い、安全で自然環境を考えた栽培を図る事を基本理念の下に、栽培した農産物を安定的に供給・販売することを目的とする。
監査所見
産地理念/事業方針
- 化学合成農薬の使用を抑え、有機肥料を使い安全で自然環境を考えた栽培を図るという理念は、パルシステムの独自基準と合致している。
- 消費者との双方向の関係を重視している点は高く評価できる。

組織・意思決定
指導部会、生産部会で役割分担され、品目別に現況及び、年度に向けた課題、また産直4原則の重要性を共有している事が会議録で確認できた。
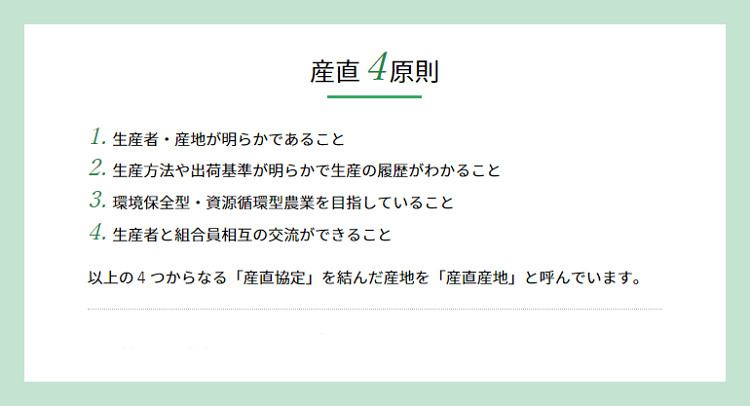
栽培基準
- 各品目が新エコ基準に基づき栽培されている事が確認できた。但し、新規加入した生産者、品目によってはエコ基準に限定された栽培ではない事が確認された。
- F-NET栽培計画書、栽培記録書で農薬散布回数や希釈倍率、日付等が明記され管理されていた。

実践内容
- 4パーミルイニシアティブを取得し、積極的に環境に配慮している。
- 圃場は機械除草だが、圃場周りの草刈り、また飛散防止の為、農薬散布は手作業で実施している。その他、疎植を実践し疫病対策を実施している。
- 農薬の保管は施錠できる場所にて保管。但し、保管の際、粉剤、粒剤等は上中断、液剤は下段に配置する等の対策が不明瞭。また農薬管理台帳と在庫の整合性は課題。

表示・出荷
- 出荷場と農薬保管庫は別の場所につき、移染の可能性は極めて低いと考えられる。
- 出荷場に衛生管理遵守事項を掲示し、各個の意識を高める取り組みを実践している。
- 出荷基準に満たない商品は、もったいない企画でロスを削減している。
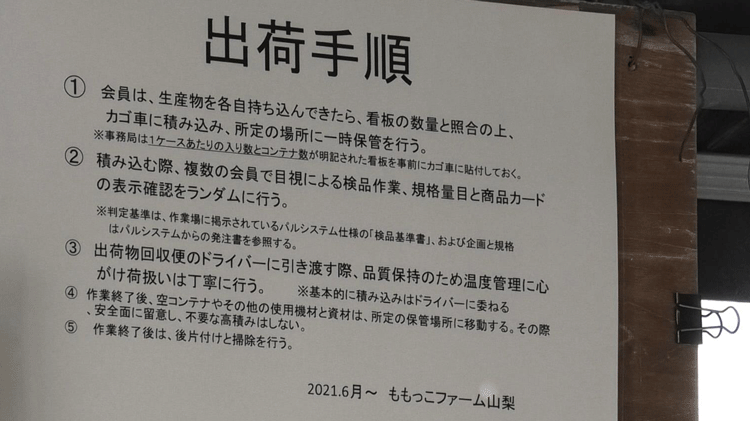
その他
- 会員は若手からベテランで構成され、新しい発想と経験で相互に協力して取り組んでいる。味や品質向上に向け、袋掛けを二重にする工夫や房の大きさを常に観察し、また病害虫への早期対策を実施する等、日々努力している。
- 土壌診断結果を参考に、現在使用している肥料等を検証している。
- 設立以降、コロナ渦により交流事業が難しい状況にあったが、地元パル山梨との交流や本会開催等、積極的に交流に取り組む意思が表明されている。
産地受け止め
- コロナ渦、組合員やパルシステムとの交流機会が減った中、公開確認会を実施し、緊張感を持ち日頃の取り組みを報告(公開)する事ができた。改めて、公開確認会の重要性を再確認したと同時に、私たちの意識変化につながったと思っています。
- 監査人の指摘については、まずはできる事から着手し、(先々において)本会を契機に飛躍したなと評価を得られるよう取り組んでまいりたい。
- 農業は少子高齢化や人口減少等、非常に厳しい局面だが、現状維持もある意味「飛躍」と考えている。高い志を持つことも非常に大事だが、しっかり地に足を付けた農業を実践し、会運営に努めていきたい。
備考(山梨県4パーミルイニシアティブ)
- 土壌中に炭素を貯留することで大気中の二酸化炭素濃度を低減し、地球温暖化を抑制する国際的な取り組み。
- 世界の土壌表層の炭素量を年間4パーミル(※)増加させることができれば、人間の経済活動等によって増加する大気中の二酸化炭素の増加を実質ゼロにすることができるという考え方に基づく取り組み。
- 2015年のCOP21(国連気象変動枠組条約締結国会議)においてフランス政府が主導で提唱し、2021年6月現在、日本国を含む623の国や国際機関が参画し、国内の地方公共団体では山梨県が2020年4月にはじめて参加。
- パーミル(‰):千分率の単位で、4パーミルは1000分の4、パーセント(%)では0.4%に相当。
株式会社ファーマン(2019年度)
■ 開催日
2019年5月14日(火)
■ 会場
大泉総合会館(北杜市)
■ 監査品目
コアフードにんにく
コアフード玉ねぎ
産地概要
産地の特徴
株式会社ファーマンは自然豊かな八ヶ岳南麓で有機野菜もしくは、化学農薬・化学肥料不使用の野菜を栽培している若手新規就農生産者です。代表の井上能孝さん自身は、北杜市に就農してから18年ほどになりますが、この地域や生産者としての想いを実現するための株式会社ファーマンを設立。ファーマンとしてはまだ3年目を迎える若い産地ですが、自称「発展途上の産地」として今回、公開確認会を開催する運びとなりました。

監査当日
監査品目はコアフードのにんにくと玉ねぎ、テーマは「持続可能な農業を目指して」です。
当日は、小雨がぱらつく中の圃場見学となりましたが、前日は晴れ間もあり、監査人は気持ちいのいい環境を感じながらの事前監査にて、圃場・施設および栽培などをしっかり確認しています。栽培に関しては、JAS有機の認証も取得していることもあり、かなり確立された栽培とさらに有機認証でも使っていい農薬を一切使っていないという揺るぎない栽培をしており、生消協野菜部会のサンドファーム旭代表取締役の金谷氏からもお褒めの言葉をいただきました。また、仲間との連携も、ライン、ドロップボックスなどを上手に利用しており、タイムラグなく常に情報共有しながら連携が図れるよう工夫しているところも、さすがだなとみなさん感心していらっしゃいました。

一番の感動ポイントは、代表の井上さんのプレゼンが内容も伝え方も素晴らしく、会場の皆さんがいっきにファーマンファンになってしまったことです。
就農し始めたときの「ヤーコン」出荷先の倒産事件から、やみくもに栽培することではなく、品目・売り先の多様性も加味しながらのリスク管理、今回のテーマでもある「持続可能な農業」を実現するために「環境保全型農業」を選択したことや、さらに未来の生産者を増やす意味でもウルトラマンやスーパーマンになりたいとおなじように「ファーマンになりたい!」と子どもたちからあこがれの存在になれるよう、諸団体と連携した農業体験の受け入れや食育カリキュラムなども実践しています。
最近話題になっている農福連携も2014年からすでに取り組んでおり、肥料の袋詰め、ラベル張り、出荷前の調整作業を始めとし、最近では栽培管理にも携わってもらいながら独自商品の開発を目指しているとのことでした。当日のお弁当も地域の福祉作業所にお願いした、ファーマンの野菜が満喫できる非常においしいお弁当でした。


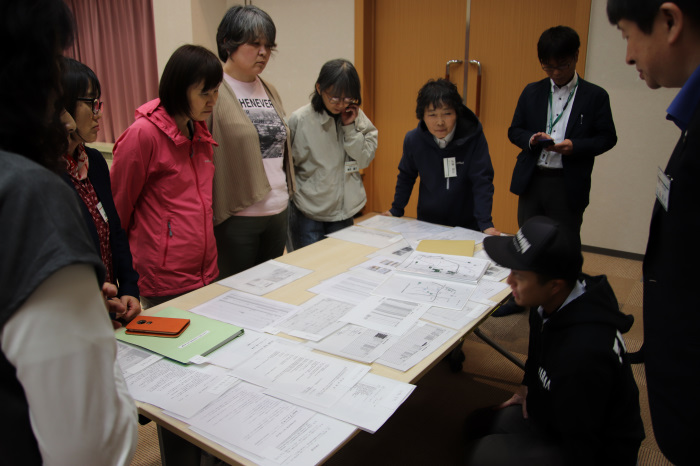
肝心の株式会社ファーマンとして運営は、正社員はまだ少ないものの、積極的な研修生の受け入れも行っており、さらに働き方も持続可能な労働環境ということで、社会保険を完備、日当たりの実働を8時間、週休2日の農場を目指しているとのお話もありました。(2019年現在、週休1.5日・年有休11~12日)その代り、農閑期には地域の耕作放棄地を開墾していく仕事も請け負い、1年中仕事があるようなスケジュール調整も行っています。
今回監査した玉ねぎ圃場やファーマンの事務所のある位置も大木が生い茂る耕作放棄地だったそうで、地域には農地はあっても長年放置したことにより、荒地どころか大木が生い茂っているケースが多く、そういったところを自分たちの手で開墾しながら、農地を拡大していることも実現しています。
産地受け止め

公開確認会は同じ野菜であってもそれぞれの産地の特徴が出るものになり、こういった深く掘り下げた内容は売る買うだけの産直とはまた違って、パルシステムの醍醐味のひとつとして毎回感動いたします。
今回のファーマンに関しては、さらに今農業の大きな課題になっている内容が凝縮されており、それらに対して真正面から向き合い、ひとつひとつ課題解決にむけて挑戦している未来有望な若者の取り組みを確認できた内容となりました。同時に、井上さんの産地受け止めに出てきましたが、「士農工商」と武士の次に食べ物をつくる農業者が重要視された時代から、一気にランクダウンしてしまった生産者の位置づけに対し、「このまま生産者が減る=付随しているいろんなものが消えていく」ことをに対し、それを生産者だけの挑戦としてとらえてしまってよいものか?と同じ山梨に住むものとして考えさせられました。

今回の公開確認会、実は「株式会社ファーマンとしてまだ、3年目なので、みなさんにお伝えできるものもまだ満足にないんですよ・・」となかなか引き受けていただけなかったのですが、私は参加者全員に「生きていくエネルギー」を与えてくれた、素晴らしい産地であることを確信しました。本当にやってよかったと思っております。
今回の確認会をひとつのきっかけとして、同じ山梨にいる者同士、いろんな形で地域を耕す関係性が作れたらいいなと思っております。
峡南鶏友会(2017年度)
■ 開催日
2017年12月7日(木)
■ 会場
いち柳ホテル
■ 参加者 48名
監査人5名、来賓1名、組合員18名、生産者2名、他生産者・他団体10名、職員12名
開会
常任理事の長谷川より、命を育てている生産者と命を食す私たちには、命の循環があり、信頼がなければ循環はない。公開確認会は、信頼関係を構築する場という話がありました。峡南鶏友会からは、生き物相手の家族経営の厳しさやそれでも美味しいたまごを届けたいという信念があって続けている意気込みなどが伝えられた。

産地プレゼンテーション
産地プレゼンテーションの他、資源循環・環境保全型農業のモデルとしておからの飼料化、さらに鶏糞の地域循環として利用し始めたグットファームからも報告がありました。鶏インフルエンザの警戒時期ということで鶏舎見学はNG。そのためにパルシステム山梨広報担当による夏から撮影した動画にて鶏舎の様子・育成状況や自家配合の餌、鶏糞処理に至るまで細かく上映。さらに生産者の苦悩や思い、夢に至るまで幅広くプレゼンすることができました。さらにパルシステム山梨が座長となって取り組んだおからの飼料化に関して、当時を知る事業本部長 黒田より説明。長きにわたって生産者とパルシステムの中で構築してきた資源循環・環境保全型農業のモデルとしての取り組みを紹介しました。


一般質問
廃鶏のことや鶏につくワクモ(ダニ)、弱った鶏の処理などの質問が出ました。抗生物質のことも質問があり、そもそも卵の業界では、抗生物質は使用しないという取り決めがあることを生産者から回答をいただきました。

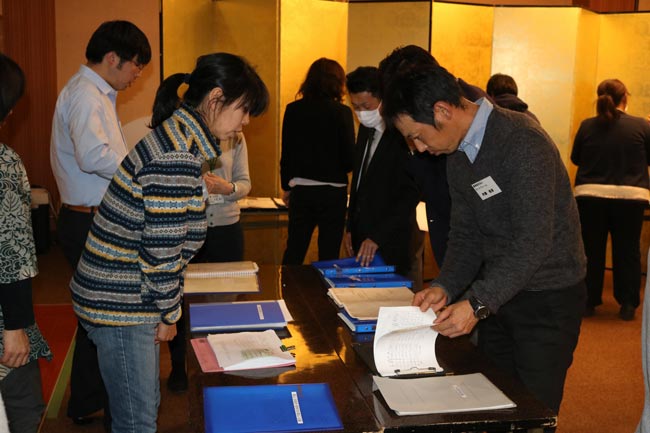
昼食
産地とも懇意につながりのある地元の“いち柳ホテル”で開催。ホテルの料理長の想いのなかで、富士川街道弁当(富士川町の特産品に特化した弁当)を出していただき、卵料理も各養鶏場から一品ずつ作っていただいた。

監査人所見
指摘として、記録の点できちんと行っているのに残されてないところがありました。チェックが甘くなっている。トレサビリティーの観点から平飼い卵がいつどこでチェックされていたのか不明。家族で行うのは大変ですので、ぜひブランディングの観点から行うことが望ましい。2代目なので出来ることもあると思います。
サルモネラの検査について。雛を購入した際に検査。その後3カ月ごと、年4回。今まで陽性反応は出ていない。出た場合は連絡し出荷停止。その後は、パルシステムと協議。万が一の時の考えた対策が書面としてあると更に良いと感じます。
自家配合肥料を使用している誠実な生産者。パルシステム山梨と築いた信頼性を保つためにも、私たちが買い支えることが必要と感じました。
埼玉でパルを利用していたが、山梨に来て産地が近いメリットを話していただいた。卵だけの独自の組織があるということで講習会に参加。自家配合飼料が素晴らしい。季節によって配合を変えている。命をつなぐ。卵1個でその事を感じることが出来る素晴らしい産地です。

自家配合肥料が素晴らしい。餌代が高くなっている。しかし卵の値段は高くなっていない。これでは日本の養鶏は成り立たなくなっているのではないかと感じました。良いものを作る人が辞めてしまうのではないか。マーケットが狭い山梨ですが、それを逆手に継続可能な養鶏が出来るよう応援したいと思います。
生消交幹事 彦坂氏
お互いに信頼しあって運営。素晴らしい。将来的に経営を強くするために共同GPの建設も考えてみていいと思います。帳票で、殺菌の紫外線の記載が漏れていましたのでそれをぜひ記載できればと思います。また、ロットごとの採卵の記録も取り組んでいただけるということでお願いいたします。

パルシステム連合会産直部長 江川氏
日本での卵を産む鶏1億3000羽。2500戸の採卵生産者。ここ10数年で半減。廃業が増えています。厳しい局面があったかと思います。印象的だったのは、2人とも自分の健康管理が重要な課題。家族経営だからこそ労働力に自分の変りがいない。怪我などの際に、経営リスクが高い。緊張感を持って取り組んでいると感じた。自家配合に労力を割くよりは、出来合いの餌の方がトータルのコストが安くなるのでは。今後もこだわりを持つのであればぜひ肥料米の使用比率を検討していただきたい。自家配合出来る施設がある。もみ米でもキロ当たり20円。餌を変えることは大きな経営判断。もし検討されるようでしたらデータ開示でのお手伝いが出来ると思います。パルシステムが仲間としていると思っていただきたい。組合員さんの卵の1世帯での利用金額111円。山梨は89円。グループ内でも非常に少ない。せっかく山梨だけに供給の生産者がいます。後継者に2人とも不安があるようですが、頼もしい生産者がいて、栄養価も高い卵をパルシステムとしてしっかり利用に繋げたいと思います。

産地受け止め
生き物を飼っているとなかなか振り返る時間がない。自由な時間のなさがプレッシャーになり暗い気持ちになる時があるが、買い支えますという言葉でリセットされ、また頑張れる。改善点を日々の中で時間を作り出してより一層データ管理を含め取り組むと宣言。山梨は、海がないが「まぐろ」の消費量は全国2位。卵の消費量は41位。立地条件として大手の企業養鶏は入ってこられないが、大手スーパーの県外産地から入ってくる卵が比較的多く消費されている。山梨のこだわりのある卵は、首都圏に出荷され、逆転現象が起きているという実態。パルシステム山梨は産直たまごも独自の平飼いたまごも県内で循環させるという究極の地産地消なので、もっと多くの方に利用していただきたい。
立ち止まって振り返ることはなかなか出来ない。この日(公開確認会)が来なければいいなと思っていたが、やって良かった。前職で周りの方に感謝して生きていくことを学んだ。組合員、パルシステム、色々なことに感謝していきたい。引き継いだ際、父親は病気で何も引き継いでいない。自身の健康管理はもちろんですが、地域の方と仲良くしたり、自分の時間を持ちながら色々な方と交流して知識を付けて行きたいと実体験に基づく生産への考え方を話していただいた。

来場者感想
県農政部
生産者とパルシステムの交流が素晴らしい。理念が共有されていることが色濃く出ている。生産者の生き残りを考えているが、その答えが「絆・繋がり」ではないかと感じました。この思いが山梨の農業の維持に繋がると思います。

消費者幹事
ユーチューブで動画を見ました。命の循環という話がありましたが、今後は情報の循環。今までの手法は大事にしつつ、若い方へのアプローチを考えることが今後の課題だと思います。


御坂うまいもの会(2015年度)
■ 日時
2015年9月4日(金)10:00~15:30
■ 場所
笛吹市御坂農村環境改善センター
■ 参加者 66名
監査人5名、来賓1名、産地参加9名、役職員51名
開会挨拶
パルシステム山梨理事長の白川より開会挨拶を行いました。昨年は2月の大雪があり、御坂うまいもの会を含め多くの生産者の方々が甚大な被害を受けました。大雪を乗り越えて公開確認会ができることを感謝しています。公開確認会は帳票や圃場を確認するものですが、重箱の隅をつつくようなものではなく、自分たちの食を支える生産者の取り組みを知ることによって、産地や地域を応援するものです。ここで学んだことを私たちの消費行動につなげて行くことが公開確認会の意義です。今の状況で農業を続けることがどれだけ大変かをお互いに理解したうえで、この公開確認会を未来の農業を考える機会としてほしいと思います。

産地挨拶
御坂うまいもの会代表の雨宮様より、受け入れ産地挨拶が行われました。御坂うまいもの会の最初の公開確認会は14年前に行われました。それ以来ずっと、パルシステムとパートナーとして歩んできました。公開確認会には時代時代のテーマがあり、14年前はファーマーズネットを利用した栽培管理や食の問題を受けたトレーサビリティの構築がテーマでした。今回はパルシステムの「新エコ基準」を理解していただくことがひとつのテーマとなりますが、「品質向上」や「おいしさ」などを改めて見つめなおして行く機会にもなります。また、5年後10年後の産地作りをどのようにしていくかという「産地ビジョン」構築へのきっかけになる公開確認会だと思っています。
事前監査報告
4月10日に行われた事前監査について、監査人の古家より報告を行いました。池田さんの圃場視察では、草生栽培などで新エコ基準に沿った栽培をしていることを確認しました。斎藤さんの巨峰圃場では、環境保全型農業を実践していることや農薬の飛散対策としてネットを設置していることなどを確認しました。産地ビジョンとして、海外への販路拡大や加工品への事業参入など、産地の今後目指す方向性があることを知りました。タブレットを使うなどの情報管理の取り組みも進めているそうです。これらの生産者の取り組みを理解し、伝えてゆくことが重要だと感じました。
産地プレゼンテーション
- 御坂うまいもの会・常田様より、産地プレゼンテーションが行われました。
-
- 産地概要、沿革
- 組織図、理念、方針、ビジョン、規約
- 事業内容
- 作業行程(葡萄、桃)
- 重点取組項目(新エコチャレンジ
- 活動紹介(内部会議、交流事業、研修
- 産地ビジョン、想いなど
- 産地プレゼンテーションの付属資料として、ジーピーエス品質管理課の松本様ジーピーエス果実課の坂本様より報告が行われました。
-
- 糖度検査結果(7月は低い傾向であったが、8月は若干の上昇が見られた)
- 品質管理(選別率の改善、PSC申告率、食味向上に向けての産地の取組み等)
帳票類の確認
作付け計画、栽培記録、出荷伝票、クレーム率記録、等
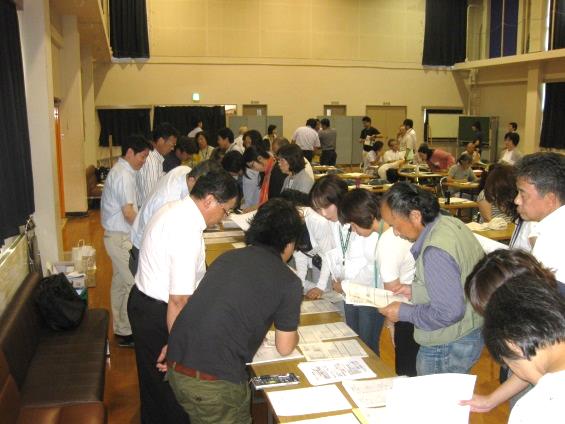
女性部の活動紹介
御坂うまいもの会 鈴木様より、女性生産者と組合員の交流会を主に担当しています。農閑期になり、甲斐路などが出始める時期には、東京でジャム作りを開催し、パルシステムの材料を使って山梨郷土料理のほうとうを作りました。交流会は去年で4年目です。これからも女性部として交流会には積極的に参加して行きたいと思います。
御坂うまいもの会 雨宮様より、昨年はパルシステム山梨の「女性生産者と組合員の交流会」にも参加させていただいた。これからも積極的に参加できるところには参加して行きたいと思います。
昼食
御坂うまいもの会より「桃」、「フルーツジャム」の試食を提供いただきました。
圃場視察
2グループに分かれて圃場視察を行いました。
【Aルート】
巨峰圃場-出荷場-保管庫/作業場-桃圃場視察
【Bルート】
巨峰圃場-桃圃場視察-出荷場-保管庫/作業場

巨峰圃場
生産者の斉藤様からの説明の後、質疑を行いました。寒暖の差があってぶどうの色がついてきますが、今年はその寒暖の差がなく真っ黒になっていません。
山梨県の圃場を見ると、葉っぱが白くなっているところが多いようですが、私たちはICボルドーを使用して、有機資材も農薬回数としてカウントしています。
出荷場
共同出荷場の確認を行いました。天候の良い時は外で検品作業をしています。検品後帳票に出荷者の名前を記入し、その後セットセンターでも検品を実施しています。
保管庫/作業場
生産者斉藤さんの自宅兼作業場を視察、確認しました。年間使用分を会で確認し、3月に1シーズンまとめて購入しています。

桃圃場視察
生産者池田さんの圃場を視察、確認しました。圃場は、7/20から約50日間消毒をしていません。
参加者より感想
フォレストファーム 中垣様
今回は出荷で忙しい時期に公開確認会を開いてくださったことに感謝します。御坂で行われている取り組みは、自分たちの理念「勝たない農業」(自然に勝つのではなく、自然界をそのままに抵抗無く対応するもの)と通じるところがある。社会も本来はそうあるべきで、そのような思いで毎日農業をしています。
山梨県農政部 五味様
果樹で農薬の5割減とは、高温多湿な山梨県では大変なご苦労をされているのではないかと思いました。生産者と相談の上で農薬を決められているとの事ですが、普段からかなりきめ細かな観察をされていると感じます。プレゼンでも、そうした努力を反映させてほしいという話がありました。価格に反映するのは消費者の気持ちとしては難しいかもしれないが、産地のことを知っていただくという点で、公開確認会の役割は大きいと思います。果物のことだけでなく、病気のことなども消費者の方に興味を持って知ってもらうのは価値があると感じます。
監査人所見
パルシステム山梨 古家理事
4月の事前監査では枝しかない状態でしたが、今回は葡萄の重みで棚が下がるほど。生産者の方の作業も大変だったと思います。異常気象の中でも農薬を抑えているのは、生産者の方が苦労をされていると思いました。巨峰の色づきの悪さは素人が見てもわかるほどでしたが、食べてみると甘く美味しかったです。見た目ではなく実際に食べてみることで全てがわかると感じました。農薬の保管庫を見て、農薬削減に努力していることを確認することができました。ぶどうは病気に弱い作物なので、病気になった房は圃場に捨てずに他のところに捨てるなどの努力も感じました。作業場は整頓されており、生産者カードも組合員へのお知らせをつけるなどの工夫がされていました。うまいもの会の理念である「おいしく、安全、安心なものの栽培」ということで、生産者一人ひとりが自信を持って栽培していることを実感し、これからも自分たちは組合員として、食べること・買うことで生産者を支えていきたいと思いました。
パルシステム山梨 甘利理事
産地の理念や事業内容も読ませていただき、丁寧な説明もしていただきました。天候不順の今年、生産者の方が一つ一つの作業で苦労されているということが理解できました。作業場はとてもきれいに整頓されていて、農薬もきれいに置かれていたので、とても安心して見ることができました。作業の細かいところも、とても丁寧にされていました。生産者の方一人一人の人柄がすばらしいことも伝わり、それが作業に生きて、果物に伝わっていることがおいしさの元だということも理解できました。
ジョイファーム小田原 鳥居様
御坂うまいもの会の8名の生産者の方は、私にとっては生産の大先生であるため、監査をするのは心苦しいところもありますが、一点、作業場で気づいたことがありました。農薬の保管庫は整頓されていましたが、農薬意外のものは入れないほうがよいと思います。
常田さんのところにカメムシが寄ったのは隣接圃場の問題があるのではないかと思います。畑をきれいにしすぎると虫が来やすいと聞いたことがあります。草を少し残してみることで解決できるのではないかと感じました。御坂うまいもの会の取組みですごいと思ったのは、全員週1回で別の人がチェックしているという点です。産地ですべてをチェックするのは大変なことなので、その点について御坂ができているのはすばらしい。
食味の確認はやっていないということですが、パルのカタログで注文した山梨の桃は、とてもおいしかったです。最後のメッセージで、エコの話があったが、農薬の基準がかなり厳しくなりました。
日本全国の消費者に安全なものを買ってもらうことを考えたときに、ほんもの実感-品質向上-農薬削減はつながってくるものだと思います。農薬削減をしているとロスが出て収益が落ちるものですが、御坂の桃とぶどうは、生産者の立場から見てかなりよくやっていると感じます。これから先は、ただ農薬を減らすことや肥料をやるだけでなく、それが“なぜ”であるのかを考えていかなければならない。これからも8名の方に教わりながら自分もやっていきたいと思います。
パルシステム連合会 島田様
桃、ぶどう、なしは、全国的にも減農薬が非常に難しい品目。その中で、新エコ基準をこれだけきちんと実行できているのは、産地のまじめさや技術レベルの高さによると、あらためてしっかりと認識できました。今年は7月後半から8月にかけての高温で、さまざまな果物の結実が10日程度進んでしまったが、そのような中、産地では苦労して出荷しています。それにもかかわらず、「今年の桃はおいしくなかった」と言われていますが、調理する野菜と違いフルーツは味にごまかしがきかないところに難しさを感じます。傷みが出ない硬さでの出荷なのか、届いたときにおいしく食べてもらえる熟度の出荷なのかは、いつも悩むところですが、当番製のチェック体制や、GPSの返品を全員で確認するなどの取り組みをしている御坂、今後の進化を期待したいと思います。
新エコで作ったのに慣行のものとして売られてしまうという問題もありました。紙面では、一定量がなければ企画することができないため、これから山梨産地間で新エコ栽培を拡大して行くことも御坂に期待したいと思います。桃とぶどうはやはり山梨がリード産地です。新エコも含めて、先進的な取り組みを進めていってほしい。若手の方もいるということで、これからの山梨産地の取り組みに期待できる公開確認会でした。今日、確認させていただいた御坂うまいもの会の取り組みや努力を、周りの方に是非伝えてほしいと思います。
産地受け止め
御坂うまいもの会代表の雨宮様より、産地受け止めとしてお話をいただきました。8.9.10月と、パルシステムの果物産地の監査が3つあり、来月は自分も福島に行く。今回の公開確認会で、生産者としての監査人コメントの仕方はこうやればいいのかと実感しました。このような場は私たちが普段やっていることを確認してもらう、自分たちの思いを伝えていくというものです。何年に一度と決まったものではなく、ニーズがあれば要請に対応して進めていきたいと思います。
参加された組合員の皆様も、この場で聞いたことを、生産者の側の立場に立って、周りの組合員の方に伝えてもらいたい。今日見聞きした「ぶどう作り・桃作りの物語」を、是非周りの組合員の方に伝えてほしいと思います。指摘された事項はすぐに改善しようと思います。

閉会挨拶
パルシステム山梨常勤理事の黒田より閉会の挨拶を行いました。御坂うまいもの会を確認し、生産者の方と会ったことで、どのようなものをどのような方が作っているのか確認できたかと思います。山梨県は果樹王国と言われていますが、桃とぶどうを特別栽培で作れるのは本当に難しいことで、農薬を減らした栽培は、野菜では進んでいるが、果樹は特に遅れています。今日お招きした五味様にも協力いただき土作りなどの研究会を進めていますが、やはた会の長沢さんにキウイのJAS有機圃場での取り組みを紹介していただきました。そういった場で話題になるのは、肥料や堆肥を減らす取り組みまでであり、農薬削減の取り組みはまだまだ実践できていません。これからも減農薬の取り組みを進めて、御坂うまいもの会の皆さんにはビジョンにある規模拡大を含みながら、もっと県内地域に出ていって仲間を増やしてほしいと思います。




