今週のうまい甲斐(4月4回)
今週のうまい甲斐(4月4回)
2018.4.14

抗生物質と耐性菌の話
今年の2月に厚労省が医者に対し、抗生物質の使用を制限するための新たな仕組みを作り、この4月から診療報酬改定に盛り込んでいます。その背景には、抗生物質に耐性をもった「耐性菌」の広がりを抑えるためでありますが、15年くらい前にパルシステムでは、すでに抗生物質の使用に対し、問題視をしていました。抗生物質は殺菌効果が高く、“奇跡の薬”として病院の治療はもちろんのことですが、同時に食べ物がつくられる農業現場でも抗菌薬として使用されており、食べ物に残留した抗生物質の摂取も重なり、耐性菌が免疫力が低い幼児を中心に病院以外でも感染が広がっていることを生消協セミナーでいち早く学んでいました。当時、米沢郷牧場の故伊藤幸吉氏が、「米沢郷牧場は首都圏コープ(パルシステムの前身)と取引をはじめたときから24年間抗生物質を使わずにやってこれました。これは買い支えてくれた組合員や生協のおかげです。耐性菌を保菌して重症化した場合、治療する術がなくなるため、そのリスクを少しでも減らしていきたい」と熱く語っていましたが、薬に頼らない飼育とは手間をかけるということであり、その非効率なコストを理解してくれる消費者がいなかったら取り組みは続けられていなかったということの象徴的な事例でした。

一般的には、価格競争のなかで効率のよさを追及することで、健康的な飼育ができず、病気になる前に予め抗生物質を飼料に混ぜていたり、肥育促進のためにも抗生物質が使われています。日本では、薬事法により、”家畜に抗生物質を最後に与えてから、抗生物質が代謝され体内から消失して出荷できるようになるまでの期間”が決まっていますが、国によっても考え方が違うので、飼育内容が開示できるような信頼できる所で購入することが安心安全の近道につながります。
どんなに効果がある薬であっても使い方を間違えると、必ず耐性をもった細菌がうまれます。今は何も起こっていないから・・という安易な考え方が、将来的に取り返しのつかないような不安材料をうむことは今までも経験してきました。生きていくうえで大事なのは、トータルして共生していくバランス感覚と、どこかだけに都合がよいことは、どこかに歪をうむという意識をもつことかもしれませんね。

できるだけ環境やほかの生き物たちとも共存できる方法で牛を飼育しています。食べ物はすべていのちであり、生きものからいのちをいただいて私たちは生きています。そうした感謝の気持ちは絶対に必要で、それがなければ子供たちにもいのちの大切さを教えることはできないと一貫した小林牧場社長の教えの中で生産者のみなさんが飼育しています。牛の健康を第一に考えた飼育を実践し、2007年に日本農業賞個人経営の部で大賞、さらに内閣総理大臣賞も受賞しています。
生産情報公表JAS認定を取得
小林牧場では安心*安全を見えやすくするために生産情報をホームページで公開しています。
健康的な飼育によって良質な赤身が主体
山梨県甲斐市の標高約1100メートルに位置する小林牧場。ここでは澄んだ空気と良質な水に囲まれ、牛たちが悠々と育っているので、赤身のうまみと上品な香りが抜群です。

必要がない薬剤はできるだけ使わない
牛を効率よく肥育するために飼料に成長促進剤を混ぜたり抗生物質を添加していません。さらに牧場内の除草も除草剤を使わず、人力と羊を放して行っています。
飼料にこだわるからこそ肉質が違う
ワインを搾って残ったブドウ粕はもちろん、トウモロコシ・オカラ・麦など、非遺伝子組み換えの自家配合飼料です。ワイン粕の酵素の働きにより、牛肉のうま味が十分に引き出されます。国内産飼料受給率を高めるために飼料米の使用を始めました。今後は地元産の飼料米を計画しています。

地域に根ざした循環型農業を実践
県内特産のワインを搾ったあとのぶどう粕を飼料として使い、牛の糞はたい肥に変えて、地元の農家に供給しています。
![]() パルシステム山梨 公式YouTubeチャンネル「小林牧場」
パルシステム山梨 公式YouTubeチャンネル「小林牧場」

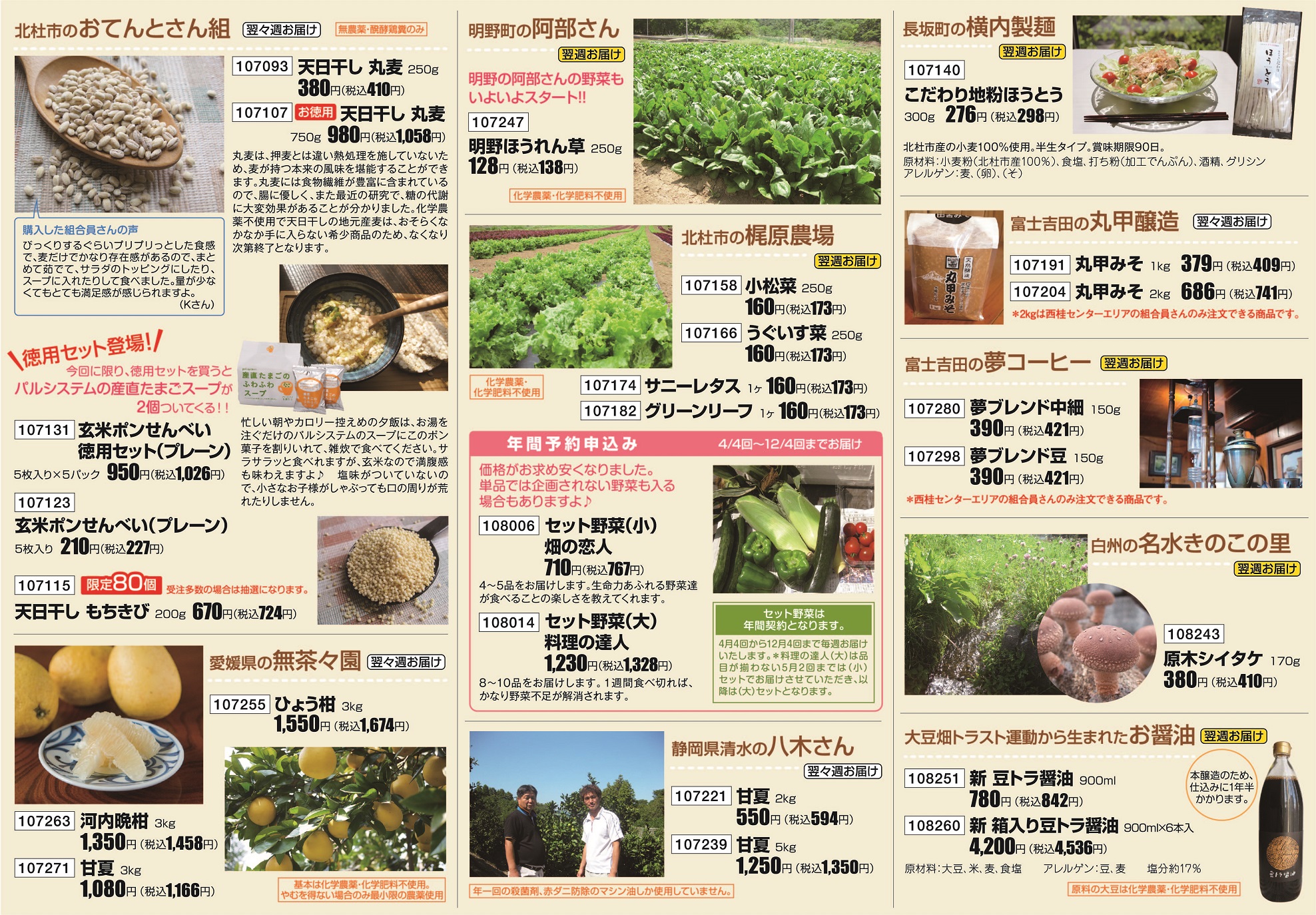
- 注文用紙もしくはインターネットでご注文ください。
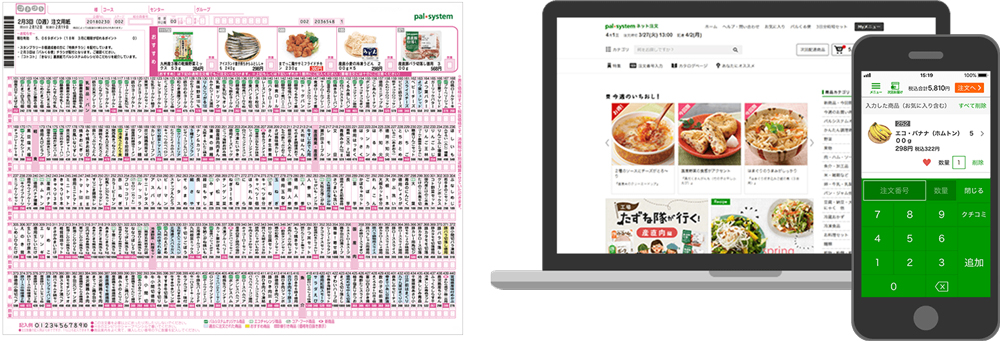
うまい甲斐5月1回






